今回、福岡のすごい偉人を紹介します。
その男の名を川原俊夫といいます。そんな彼のお話をします。
今回、「【ふくや】創業者の川原俊夫のストーリーがすごかった。めんたいこで市場を開拓した男の話。」
を読むことで、ふくやという明太子の会社がどれほど九州の経済に貢献したかがわかります。
商売は自分のことばかり考えていてはいけないということに気づかされます。お客様が求めているものを提供するのが商売人だということがわかります。ということで是非お読みください。
なお、この話は、木下斉氏のボイシーチャンネルより、引用させていただき記事としました。
現在、コロナの影響で実店舗での営業がかなり厳しくなっております。
リスクも当然高いです。一番大きいのが感染症対策ですね。本当に大変だと思います。
ですが、よく考えてください。これは、実店舗でできないというピンチであり、別のやり方をやっていかなければいけないという事に気づかされた言わばチャンスでもあると思うのです。
市場規模1900億円をつくった川原俊夫
2007年に明太子の市場規模は1900億円になりました。
現在でも1200億円という市場であり巨大産業となっています。この市場を開拓したのが、ふくやをつくった、川原俊夫です。
川原俊夫は明太子を世に知ってもらって、結果たべてもらえばいいとう大きな器を持った人であります。
川原俊夫は1913(大正2年)韓国釜山に生まれました。
川原家は明治後期に筑前から釜山に渡りました。当時は、筑前から釜山へ移動する人も多く、釜山では2万人にかたが当時さまざまな商売を行っていました。
川原俊夫は南満州電気株式会社に就職、その後1936年(昭和11年)に結婚。1944年(昭和19年)陸軍に召集され太平洋戦争へ行って、宮古島で終戦を迎えました。
1948年(昭和23年)中州市場へ移住、食料品店「ふくや」を開業し、食料品を販売しました。商売は好調であり、川原俊夫は「ふくやも目玉商品がほしい!」と考え、釜山時代で知った明太子、たまご付のものをアレンジして、これを売ろうと商品開発を行いました。しかし、なかなか売れず、つくっては捨てる状態でした。
やっぱり、あの見た目のものを買ってくれる人はなかなかいないですよね。
今でこそ、おいしいから、見た目も問題ありませんが、初めて食べようとは思わないかもしれません。
10年たってようやく売れた明太子
中州市場の近くには小学校があり、昼ごはんのおかずのたしにの少しずつ売れるように、近くの中州の小料理屋 も取扱はじめ、少しずつですが売れるようになったんです。
そして、さらに、なにより変化したのが、福岡の出張客が、おみやげに何かないかと、明太子を物珍しさに買いはじめ、すこしずつ全国に広がっていったのです。
その後、1975年博多止まりの新幹線開通したことで、爆発的に人気商品となったのです。
そこから、いろんなお店がふくやへ、商品を卸したいと依頼が来るのですが、川原俊夫は、ふくやは明太子卸の卸をしないといいます。明太子は生ものであり、管理状況が悪くて、あってはならないというわけなんですね。
ふくやは、自ら製造販売を一貫して行うので、ふつうならうちにしかできないようなノウハウは教えないし、特許などとって、独占商売しますよ!
だけど、川原俊夫は、そんなに売りたいなら自分でつくったら?
そして、卸したいという人に、明太子の作り方の概要を教えるのです。具体的な調味液はおしえなかったらしいのですが、普通ここまでしません。
川原俊夫は、支店出して、工場だして、大きくすれば管理がずさんになるといい、一級品のたまごと一級品の調味液で、お客様に届けたいと言うのです。
川原俊夫はマーケットクリエーションを行っていた
明太子は珍味っぽいですよね。だけど、ちがう!これは惣菜であり、漬物と一緒だというんですよね。
「だれが漬物の作り方かくしますか、漬物だって付け方が違うし、どれがおいしいかはお客様が判断するものだ」というわけなんですよ。
マーケットクリエーションとは、従来ない市場をつくる。ということをすでに、行っていたのです。
明太子を広げて、結果みんなが食べるようになって、そして、うまい明太子を食べたいと思ったらふくや
に来てくれればいい、というわけなんです。
そして、1975年の新幹線の博多開通で一気に明太子が出張客に大人気となりました。50社ほどが参入し驚異の成長を遂げました。
当時直営店中州本店、薬院店のみ販売でしたが、店の前には100mの行列ができていました。
通信販売事業へ
この事業は息子さんの、健(たけし)と正孝(まさたか)の2人の兄弟に継承され、
これから、さらにふくやはもっと、生産性をあげたいと強く思います。
福岡相互銀行(現・西日本シティ銀行) につとめていたこの2人が、事業継承して長野県小布施町の竹風堂(ちくふう
どう)のクリーンルームの視察に行きます。ここですごいものを見るのです。
机と電話二台しかない部屋、竹風堂さんは、「ここはなんだと思う?」と問うのですが、当然わかりません。
実は、この部屋はオペレータが電話注文を受けて、そして、ここから商品を発送し、ここで1億の売り上げ
るというのです!これには、二人は衝撃をうけます。
ふくやは明太子業界では店舗数も少なく、業界売上高3位。自分たちがつくったのにおいしければ儲かると思いやっ
てきたのに、なかなか結果がでない、挽回できないところへチャンスが来たのです。
多店舗展開も非効率だし、通信販売を積極的におこなうか!
福岡シティー銀行に当時つとめていた時、コンピュータの電算システム導入を銀行業務でコンピュータをいれて一気に効率化改善した経験があります。
その経験を活かし、さらに、ただ電話を受けるではなく、コンピュータを入れて独自の通販用顧客データ管理システム、自動印刷までできるシステムを開発し、
少ない人員で注文から発送までできるシステム構築をしました。
今まで、東京のお客さんなど常連客が電話注文できる!ということで爆発的に売れました。当時電電公社回線がパンクしたほどです。
その後、一気に年商100億円 現在は通販が売り上げの半分を占めました。
さらにこれでは終わらなくて、息子さんたちは、この通販システム、いろんなところに教えたのです。
結果、九州は今や通販大国であり、ジャパネットたかた、やずや、キューサイ、青汁のアサヒ緑健
などは九州発であります。
この通販大国のしつけ役として、ふくやはがんばり、現在通販市場は2000億円であります。
川原俊夫はこれほどバンバン儲かっているが法人化もせず、税金もばんばん払い、さらに
博多山笠祭りにもお金をバンバン出し、町にどんどん還元していったのです。まさに商人の鏡ですね。
今でも、ふくやは、スタートアップ事業や、若い人挑戦にはスポンサードとしてついており、そういった面の支援も行っています。
明太子一つで、本当にすごいですね!
町の形成には、立役者が必ずいて、それが二代目以降もしっかりと受け継がれ、通信販売事業など今日の地域産業を支えているのです。
どうですか?川原俊夫すごい男ですよ!
まとめ
今回は「【ふくや】創業者の川原俊夫のストーリーがすごかった。明太子で市場を開拓した男の話。」についてお話してきましたが、いかがだったでしょうか。世の中を変えるのはみんなだければ、きっかけはたった一人の行動からはじめるのですね。
どうですか?こういったストーリを知りながら、ふくやの明太子を食べるとおいしさがまた、違うでしょう!
食べたくなりましたか?
以上です!
興味がある方、購入して食べてみてくださいね。それでは!

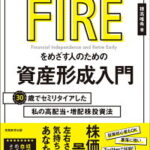









コメントを残す